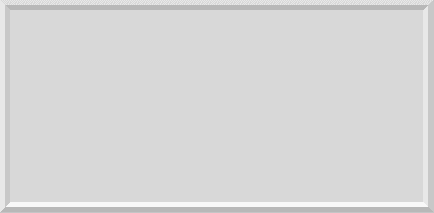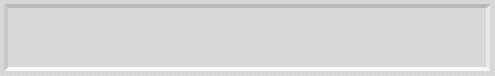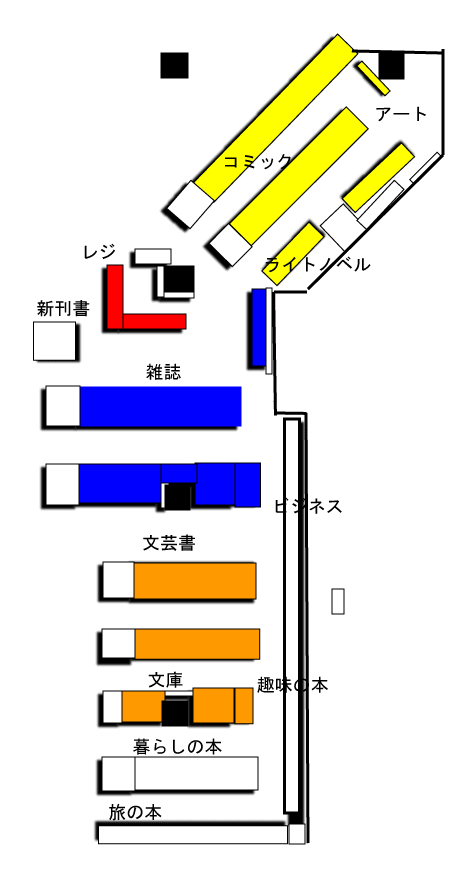
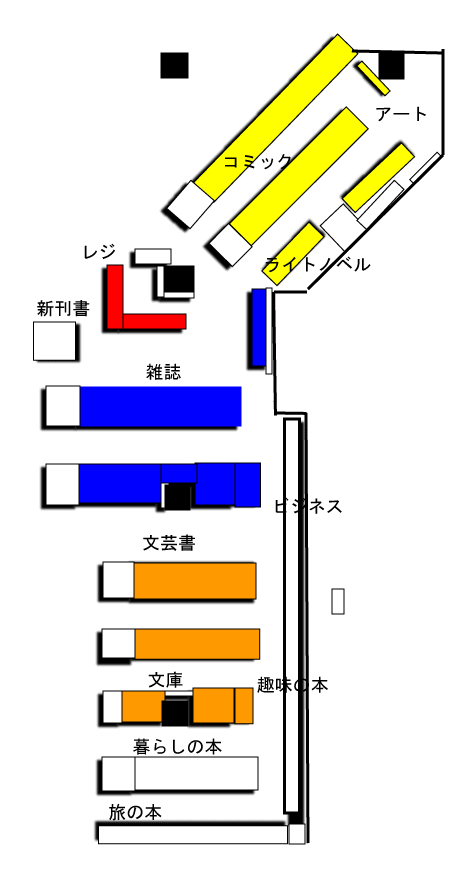
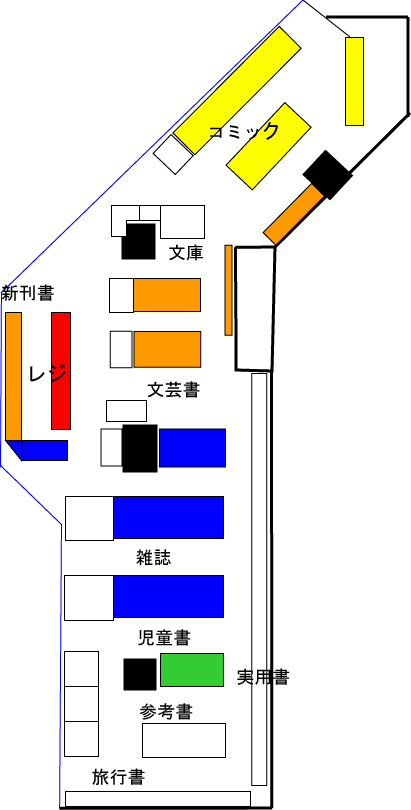
駅前のショッピングセンタにある70坪のA書店。駅の乗降客は2万2千人。改札口は3階にあり、改札前の広場を出ると、駅前ロータリーにでる階段とショッピングセンタの入り口通路に別れる。
ショッピングセンタに入るとすぐに中央に島地の売り場があり、右側通路奥にA書店を確認することが出来る。駅周辺に書店はない。
通勤客の動きは、朝は駅前ロータリー口から上りのみのエスカレータで駅に入り、帰りには約半数がショッピングセンタを通って家に帰るとみられる。ショッピングセンタの入り口に入ったところで通路が二手に分かれ、3分の2が左の通路に向かう。その先にエスカレータがあり1階の食料品売り場へと続く。
A書店は右側の通路の途中にある。乗降客のみで考えれば、帰りの通勤客を中心に1万1千人の半分で5千500人。その3分の1で1833人。店前のお客様の流れは、ほとんどが駅側入り口からの通行となっていた。
具体的な数字を得るための店頭通行量チェックはしてはいない。
開店以来、5年間は月商1000万円を前後していたが、その後の5年間は減少傾向にあった。直近の1年間は対前年で―14%まで下がっていた。リニューアル前の月商は750万円から850万円。
<なぜ売上が下がってきたのか>
1、客層の変化。
直接的には、近くの駅に大型のショッピングセンタが出来たためと、対抗する別の駅にあるショッピングセンタが大掛かりな宣伝を行った結果、当該ショッピングセンタの集客が連続的に落ちてしまったという経緯である。
A書店はショッピングセンタの主婦層と通勤客それに近隣の高校生を主要客層としていたが、食料品の売上が下がる状況の中で、主婦層の来店自体が減っている。特に土日に来店する子供づれが極端に少なくなった。
通勤客に対するアプローチはしてこなかったが、客数が減少する中で相対的に通勤客などサラリーマンと思しきお客様が目立つようになっているとの認識はもっていた。
A書店では、来ていただいている客層と店の商品構成が適合しているか、ということを調査したことはなかった。
2、レイアウトの問題。
まずレジ位置が悪いという印象。細長い店舗なので全体が見渡せるという意図での配置だが、そのために全体の商品構成を分断させている。
雑誌は1600mm幅の棚が2台と800幅が1台の構成で、全体の商品構成上からも雑誌が少ないと感じられる。その上、売れ筋の雑誌や話題になっている雑誌の品切れが目に付く。
文芸書や文庫はレジ前にあるが、一列が800幅の中棚が3台(2m40cm)という構成で、棚前に立ったときのボリューム感に欠ける。しかも新刊はレジ後ろや柱周りの平台にあり、連続性がなく買いづらいと感じる。
実用書は入り口側から雑誌の奥の壁面に展開されているが、学参で分断されている。
コミックは、万引き対策のために通路は閉鎖されている。この件は改装後の課題となるだろう。
お客様の導線は、駅側の入り口方面の通路からレジに向けている設計なので、旅行書、児童書、雑誌がラインの中心となっている。
基本的に管理面を重視して棚配置を構成した設計になっている。
サイン表示がばらばらで、分かり辛い。回りの店舗と比べて照明が暗い。
3、商品構成の問題。
どのような客層に対してどのようなグレードの商品を販売するという方針が立てられていないと感じた。独自の品揃えというわけでもなく、全国の売行き良好書ベスト100あたりでも欠本が目立つ。
理由を聞くと、この店では売れないからという判断であった。
過去に「売れたから」という自分の判断を元に補充なり注文を行なってきた。売上がおちているのだから、自分の判断を一度リセットしてみるべきであろう。
雑誌が中心にあるにも関わらず、その雑誌に手が入っていない。改正がうまくいっていない為か基本雑誌の欠本が目立つ。ここでも売れないからという判断であった。
最新刊の書籍と文庫はレジ前にはあるが、新刊と棚の関連が分かりづらく、棚も平台もボリュームが極端に少ない。在庫金額と返品率を気にしていることは良いのだが、これだけ売上が下がってくると悪循環に陥る危険があることにもっと注意をはらうべきだ。
コミックの陳列にしても、ライトノベルや攻略本、アート関係がまとまっておらず、判型に従った旧態依然の陳列となっている。
主婦層に対するアプローチも初歩的な品揃えの本ばかりで工夫がない。通勤客に対するアプローチはほとんど行なわれていない。学生に対してはコミック以外の提案がない。
要するに、相対的に強いと思われるジャンルが店舗の中で目立っていない、ということを解決しなければならない。
4、接客の問題。
第一に、この店の責任者が「私は正しいことをしている」と主張する姿勢が問題であると感じた。
自分の主張は、販売に結びつく結果がなければ意味のないことだと認識すべきという基本のところでつまずく。売ることが目的になっていない。
お客の要求する接客を行なっていないともいえる。近年、接客に力を入れている店舗が大半を占めている現状では、総合型の書店であれば少なくとも標準以上の接客を行なわなくてはならない。
自分が良いと思うということも重要ではあるが、お客様の目線で判断することの方が最優先である。
これは接客を重要と考えていない典型であった。販売である以上、何もしないという接客はありえない。時間のかかる課題である。
仮にその店独自の接客を追及するなら、さまざまなアプローチを行い検証することがなければならない。いずれにしてもお客様に対する行動を起こすという意識を持つことから始めて、主導権は店側が持った上で接客を行なうという姿勢を構築しなければならない。
隠れたクレームについては今回の目標からはずした。
<具体的な対策>
この店舗を利用するお客さまの立場を理解しているか。その目線を理解しているか。要するに、店舗はお客の要求する状況を把握しているか。ということを再確認することからはじめる。
1、仮説、対策
働いている人を主要ターゲットに設定した品揃えをする。
ショッピングセンタが売上を下げている状況は変わりそうにないので、通勤客を取り込む工夫をする。
売上が見込まれる分野を強化、拡大する。満遍なくあるのではなく、ある分野は多く、ない分野も存在する。高校学参は注文のみにする。
棚が分断されているので、ジャンルのボリュームを持たせるために棚を連続させる。それにより、主要ジャンルに対して商品強化を行なう。
商品構成は、リセットして全国の売上状況を反映することからはじめる。駅前立地として構成しなおす。
平台は、新刊の売行き良好書と意識的なフェアで構成する。新刊の売れ筋から外れた商品を使いまわすことはしない。見切りをしっかりつけることを要求する。
問題の接客については、注文品を意識的に取ることを従業員全員に課して、作業中でもお客様に向かう姿勢をつけることからはじめる。
宣伝が足りないので、予算をつけて宣伝する。
2、レイアウト
レジは、店員がお客様に向かって立つように配置する。会計のお客様がいないときは、店内に向かってアイコンタクトをしながら挨拶を行なう姿勢をとる。
売行きの立っている雑誌とコミックと文庫、それに趣味実用の4ブロックを重点分野とする。
中棚の一列は以前の倍である800幅6台(4m80cm)を基本とした。これで以前よりはジャンル毎の商品ボリュームがでる。雑誌は、1600幅を4台と柱を挟んで3台半とした。
3、商品構成
雑誌は、基本在庫を駅前立地という設定で再度構成しなおす。売れている雑誌はそのままに、売れていないか在庫がない商品は、基本の雑誌を出来るだけ面陳で置いて売る努力をする。ジャンルとしては趣味とくらし関係の雑誌を充実させる。
コミックは、アート関係とライトノベルを構成ジャンルに追加し、青年コミックを充実させる。
文庫は、棚に置く作者を特定する。文芸書とともに作家重視の陳列に変更する。
文芸書は、作家フェアを常時行なう。
趣味実用書は、くらし、趣味、旅に分ける。くらしは、生活スタイルの提案を商品構成の核とする。趣味は、売れている入門書の次のステップを陳列の中心に置く。旅は、地域情報や歴史を含め、その地域に対する知的興味を商品構成の中心とする。
児童書は、絵本を日本、外国、よみきかせ、昔話に分けて表紙陳列を6段とる。童話は、ファンタジーと冒険・探検を充実させる。
ビジネスは、資格、就職、検定、法律を含める。多すぎる自己啓発を減らし、時事関係を充実させる。日本コーナーを作る。
4、効果の測定
来店客数を増やすために駅側のショッピングセンタ入り口通路で、定期的にコミック新刊、創刊雑誌、話題の本等の店頭販売を行なう。チラシ配布。
B本や、文具割引販売、フェアのお知らせなどで、近隣に新聞折込チラシをまき宣伝する。
店頭でもフェアのお知らせチラシをまく。
狙ったジャンルの売上推移の増加傾向。
夕方の通勤客に対するアプローチは適正か。
お客の要求する商品を知るために、訪ねられた事柄は全て記入し朝礼で全員に発表することにした。特に新刊ではどのジャンルを聞かれるのか。
注文を受けることを意識しておこなうように、個人別に注文数の目標を立てる。注文状況をみて不足ジャンルや商品を見つけ出す。
注文していただいたお客様を通して、主要客層について絞り込みを行なう。
来店頻度とフェア期間の関係について調査する。
そのほかには、この状態を維持するために、棚担当者が毎日きちんと商品に向き合っているかをチェックする。
5、実際の効果
改装後、翌月は対前年伸張率が105%、翌々月115%になり、そのまま推移している。売上は950万円を超え12月は1150万円に回復した。
引き続き、宣伝の継続と接客の向上を図る。目標は月商1,000万円を切らないこと。